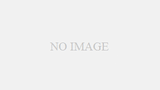こんにちは。ぺちです。
内定率1%とも言われているAmazon Japanの採用試験。
今回はその面接で重要な「スケーラビリティ」という考え方について解説します。
「スケーラビリティ」とは
あまり聞き馴染みがない言葉「スケーラビリティ」ですがAmazonでは業務のなかで耳にタコができるぐらい聞く言葉です。Amazonではスケーラブルとも言ったりします。
「スケーラビリティ: Scalability」とは
拡張性がある、つまり、利用規模の増減に合わせてシステムの性能や機能を柔軟に拡張できることを意味します。主にIT分野で使われ、ユーザー数の増加などに伴い、品質やパフォーマンスを維持しながら、コスト効率よく対応できるシステムの能力を指します。
Amazonでスケーラビリティを重要視する理由
Amazonではこのスケーラビリティ/スケーラブルという考えを非常に大切にしています。
その根底には「Good intentions don’t work, mechanisms do」というジェフ・ベゾスの思いがあります。
Good intentions don’t work, mechanisms do
このジェフ・ベゾスの想いは意訳すると「個人が気を利かせて進む業務は意味がない、メカニズムで解決すべきだ」ということです。
よく業務を進める中で〇〇さんならできるけど□□さんはできないよね。というシーンはよくあるかと思います。ですがこれでは〇〇さんが病気や退職でいなくなった場合、業務が回らなくなります。いくら〇〇さんが頑張って組織の業績が上がったとしてもこれでは意味がありません。
「それはスケーラブルなの?」という言葉が会議では飛び交う
一方、Amazonでは誰がやっても同じアウトプットができる仕組み(=メカニズム)を作ることこそが大切であるという考えを大切にしています。よって新しい事業を行う時には「そのやり方はスケーラブルなの?」とよく上司に聞かれました。
スケーラブルにするとはどういうことなのでしょうか。例えば
・毎週金曜日にこの業務を〇〇担当の人が行うこと
・業務を誰でも行えるよう、手順書を作成して全員に配布すること
など、どんな状況でも、何年後でも、他の支社でも昨日する仕組みを作ることですね。
これにより人に依存せず、組織として安定してお客様に貢献でき、利益をあげることができる。そんな組織を作りましょう。というのがジェフ・ベゾスが提言した言葉から派生したAmazonの考えです。
面接でも必ず確認される「スケーラビリティ」
ではAmazonの採用面接に話を戻しましょう。
面接の結果を話し合うデブリーフ会議でも「この候補者の出した成果はスケーラブルか」ということを確認します。
※デブリーフ会議についてはこちらの記事で解説しています。面接対策とは話が逸れますが、Amazon特有の中々面白い仕組みなのでぜひご覧ください。
面接におけるスケーラビリティとは前述のものとは少し違い、応募者の持っている力がAmazonでも発揮することができるかという意味になります。
前職の職種だったから、ポジションだったから力を発揮できたが、Amazon入社後に同じ力を使って成果を上げていただかないと意味がありません。
よってその力をAmazonでも発揮できる拡張性が面接では聞かれます。そしてデブリーフ会議で議論されます。
面接でどのように「スケーラビリティ」を表現するのか
ではどのようにスケーラビリティがあると面接で表現すれば良いのでしょうか。
これこそが「OLPを発揮できる人材である」ということを面接で話すこととなります。
OLPは仕事をする中で重要となる思考や価値観のことであり、これは環境には依存しません。皆さんがどんな場面においても持っている力であるからです。
よってきちんとOLPを体現できるということを面接で話すことができれば、それがスケーラブルにAmazonでも力を発揮できることに繋がると考えます。
なおOLPに関してはこちらの記事で解説していますのでぜひご覧ください。
最後に
今回はAmazonが大切にしているスケーラビリティについて解説しました。
この考え方は新卒/転職の面接においても確認される点であり、入社後もたくさん聞く機会があると思います。
本ブログでは元Amazonの面接官である筆者が転職の対策やAmazonで働いたからこそ知る小ネタをたくさん投稿しています。
他サイトでは紹介できないような、元面接官だからこそ解説できる細かい内容も記事にしています。(今回の記事はまさにこういった細かいですが重要なポイントです)
他の記事もぜひご覧ください。